相続した実家の家屋が未登記だったとわかったら、そのままでは売りに出せません。
家の売却の前には表題登記が必要ですが、他には家を解体して更地にする方法もあります。
未登記の家を売却した経験から、未登記の対処法をお知らせします。
相続した実家の家屋が未登記だった
相続した実家を売却しようと動き始めましたが、なんと接道する道路が公道の市道だと思ってばかりいましたが、持分なし私道であることが判明しました。
このままでは到底売れないということがわかり、不動産屋に相談したり、自分で書類を見たりして次にわかったことが、家屋が未登記であるということでした。
家屋が未登記かどうか調べるには
家屋が登記済みであるかどうかは、固定資産税の支配の通知にある「資産の評価」欄に記載されているので、すぐに調べられます。
うちの場合は、新築後に父親が家屋の建築を請け負った会社と建物の不備に関して争いになったようです。
父自身が亡くなっているのでいまいち事情が判明しませんが、通常は売却元である実家の建設会社が行うように手はずをするはずの表題登記がしないままとなったのではないかと思います。
また、家の場合は住宅ローンを一切組まずに、土地と建物代金の全額を父の退職金の現金で支払ったため、登記を前提とした手続きが要らなかったためもあるようです。
ただし、固定資産税の請求は家屋が未登記のままでも請求があり、もちろんそれまでも滞りなく支払われていました。
売却するには表題登記が必要
住んでいる場合には特に問題はなくても、未登記の建物を売買するということは通常はありえません。
建物が誰が所有するものかがはっきりしないためです。
実家を売るためにはまず建物の表題登記をしなければなりません。
未登記の家屋もあるが
ただし、未登記の家屋はそうめずらしいことでなく、そこら中にあるとも言われています。
なので、その時売却を相談していた不動産屋さんもそれほど驚きもしませんでした。
未登記なので法律違反になるのではないか、何らかの罰則があるのではないわからないうちは心配になりましたが、特にそういうこともありませんでした。
未登記家屋は売却できない
そうは言っても、表題登記には費用もかかるのはもちろん、問題が一つ増えることになります。
土地家屋込みで買い取りを依頼したときに、断りの理由に「底地」と言われたことがあったのを思い出しました。
人の物の家がある場合の、その土地だけの売買となるという意味のことだと思います。
建物と土地と両方の登記が行われ、その名義が一致しているのが普通であり、売却するときの最低条件でもあるのです。
地価の高い都市部には、建物と土地の名義が別々であったり、土地の身が抵当に入っているなどという例もあるかもしれませんが、あくまで田舎の、しかも比較的新しい方の郊外型団地の住宅地では聞いたことのない話です。
未登記家屋の解体は
もし、この家屋を解体するとしたらどうでしょうか。
そもそも登記をしていない建物は、その土地に建っていないというのと同様の扱いになっています。
なので、家屋を解体してしまえば登記は関係はありません。
建物を壊すというときは、相続人一人の意向でも依頼はできると聞きましたが、その際は取り壊し費用を私一人で負担することになってしまいます。
それ以上に、相続登記そのものに兄弟の同意が取れない時に、同じく同意があるのが望ましい保存登記を一人で進めるということはたいへんなことでした。
結局、表題登記は、業者買取が決まってから私が自分で行うこととなったのですが、通常は登記を依頼するということになります。
表題登記の依頼先は
表題登記の依頼先は、土地家屋調査士という士業の人となります。
もし、既に不動産店に売却を依頼しようという時でしたら、不動産会社が手配をしてくれます。
また、相続の相談を通じてすべてを依頼することもできます。
下の相続の窓口なら、売却まですべてワンストップで依頼が可能です。
相続の窓口 相談無料!
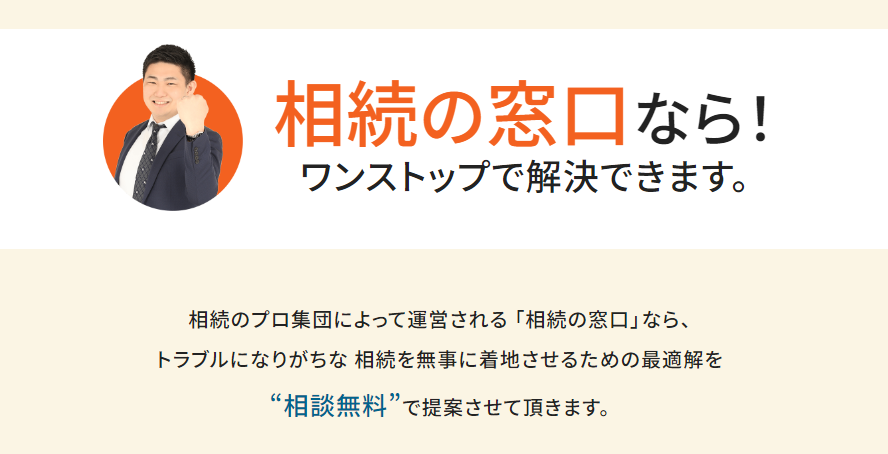
ラクウルを運営するネクサスプロパティマネジメントが併設する相続物件の相談に利用できるのが”相続の窓口”です。
相続の手続きと合わせて土地を売却したいという場合は、こちらかから無料相談を通して依頼をすることができます。

相続の手続きにはそれぞれの専門職に別々に依頼をすることになりますが、「相続の窓口」を利用すれば一度の相談で済みます。
- 相続税の計算⇒税理士
- 相続の手続き⇒司法書士
- 相続物件の評価額⇒不動産会社
- 相続物件の売却⇒不動産会社
不動産会社運営のラクウルが併設する相続の無料相談なので、不動産の分析、土地や家屋の買取と合わせてすべてワンストップで依頼できます。
相続手続きがたいへんという方、相談は無料ですのでお悩みの点を相談してみてください。
相続全般の問題の無料相談
>>【相続の窓口】へ
不動産買取と相続を合わせて依頼
>>ラクウル公式ページへ
※相続の窓口詳細については下の記事に
相続と不動産の相談の両方が依頼できる「相続の窓口」